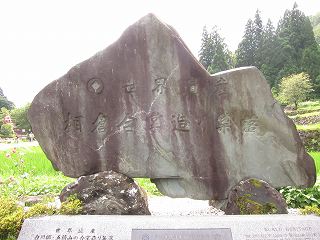|
THE WORLD HERITAGE Asia No.asia07 |
|||
|
国名 |
日本 |
||
|
遺跡名称 |
白川郷・五箇山の合掌造り集落 |
||
|
登録年・遺産種別 |
1995年・文化遺産 |
||
|
訪問日 |
|||
|
参照サイト |
|||
|
|
■白川郷・五箇山の合掌造り集落 飛騨地方の白川郷(岐阜県大野郡白川村)・五箇山(富山県南砺市)にある合掌造りの集落で、1995年12月9日にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。 ■白川郷・荻町集落 合掌造り住宅59棟が残り、世界遺産登録面積の約3分の2を占める。 |
||
|
■合掌造りは、江戸時代から始められた蚕産のため、屋根裏に棚を設置したのが始まりといわれている。豪雪による雪下ろしの作業軽減と屋根裏の床面積拡大のため、急な角度を持つユニークな茅葺屋根になったと考えられている。又、屋根はどの家屋も東西を向いている。これは屋根に満遍なく日が当たるようにするため、集落が南北に細長い谷にあり、南北それぞれの方向から強い風が吹くので、風を受ける面積を少なくするためといわれている。
|
|
||
|
|
■合掌造りを守る地域住民の連携形式の結(ゆい)により、補修や茅葺の葺き替えが行われている。 ■白川郷・五箇山の集落地帯は、有数の豪雪地帯のため、周囲との交通路整備が遅れた。このため、奇跡的に合掌造りの住居構造が残った。しかし、過疎化・住民の高齢化により、結の活動による、合掌造りの維持活動も限界となっている。 ■世界遺産登録後、急激に観光客が増加。近くを走る高速道路(東海北陸自動車道)の全面開通も2007年度に迫っており、地域社会の生活と観光地化の狭間で、様々な問題も発生している。
|
||
|
|
|
||
|
|
■家屋の東に、家人や客の出入口であるドジ(玄関)とシャシ(取次場)がある。ドジの南にヘンチャ(便所)、西側へと順番にマヤ(牛馬飼育室)、ウスナワ(作業場)、ミンジャ(勝手場)と続く。ミンジャは、谷川の水を取り入れるところでもあり、その脇にはスウル(風呂場)がある。スウルから出た後には、必ず仏前に合掌する習慣があった。 ■中にあがると、手前にオエ(居間)、その西にダイドコ(食堂)があり、どちらも部屋の中心にユル(囲炉裏)が設置されている。オエは広い板の間で、応接間や食事の場としても使われ、家族の語らいの場でもある。ユルの周りにはヨコザ、カカザ、オトコザ、シモといった座位があり、ユルの中央には三徳と呼ばれる鉄製で三ツ足の輪が置かれる。三徳は、上に鍋を乗せて汁物を作ったり、団子を蒸したりするのに使う。ユルの上には、「火アマ」と呼ばれる板製のおおいがあり、四隅を太い縄で吊してある。火アマは、火の粉が飛んでも直接アマの方へ行かないように、ガードの役割を果たしている。 |
||
|
■20年ぶり白川郷に再訪したところ、その環境は一変していました。東海北陸自動車道が開通し気軽に訪れることができるため、集落へは車乗り入れ禁止になっていました。また昨今の訪日観光客増加により、日本人より外国人の方が多く、特に冬ということもあり雪を知らないタイやベトナムの方が多いようでした。 |
|||
|
■駐車場から集落に入るために渡る「であい橋」は人だらけ。 |
|
||
|
■明善寺。 |
|
||
|
■雪を被った合掌造りの明善寺庫裏。今年は雪が少ないようです。 |
|
||
|
■雪ではしゃぐ外国人。 |
|
||
|
|
■五箇山・相倉集落 合掌造り住宅20棟が残る。 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||